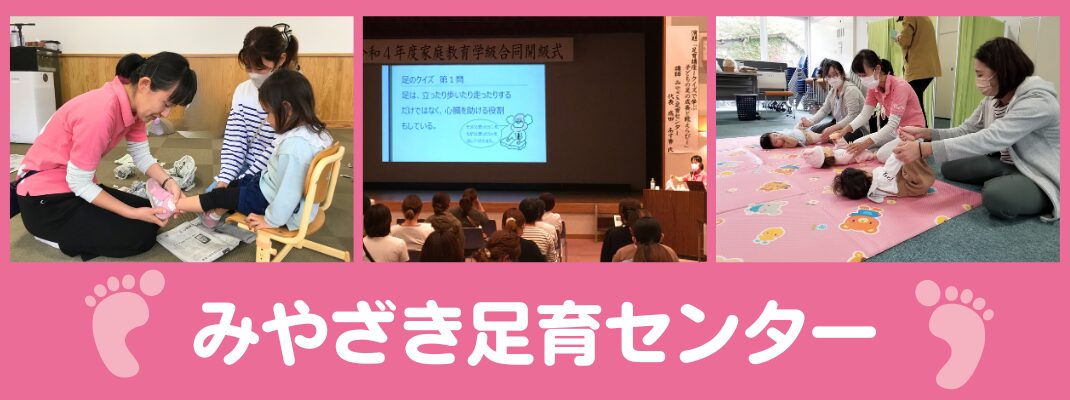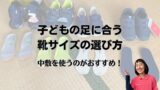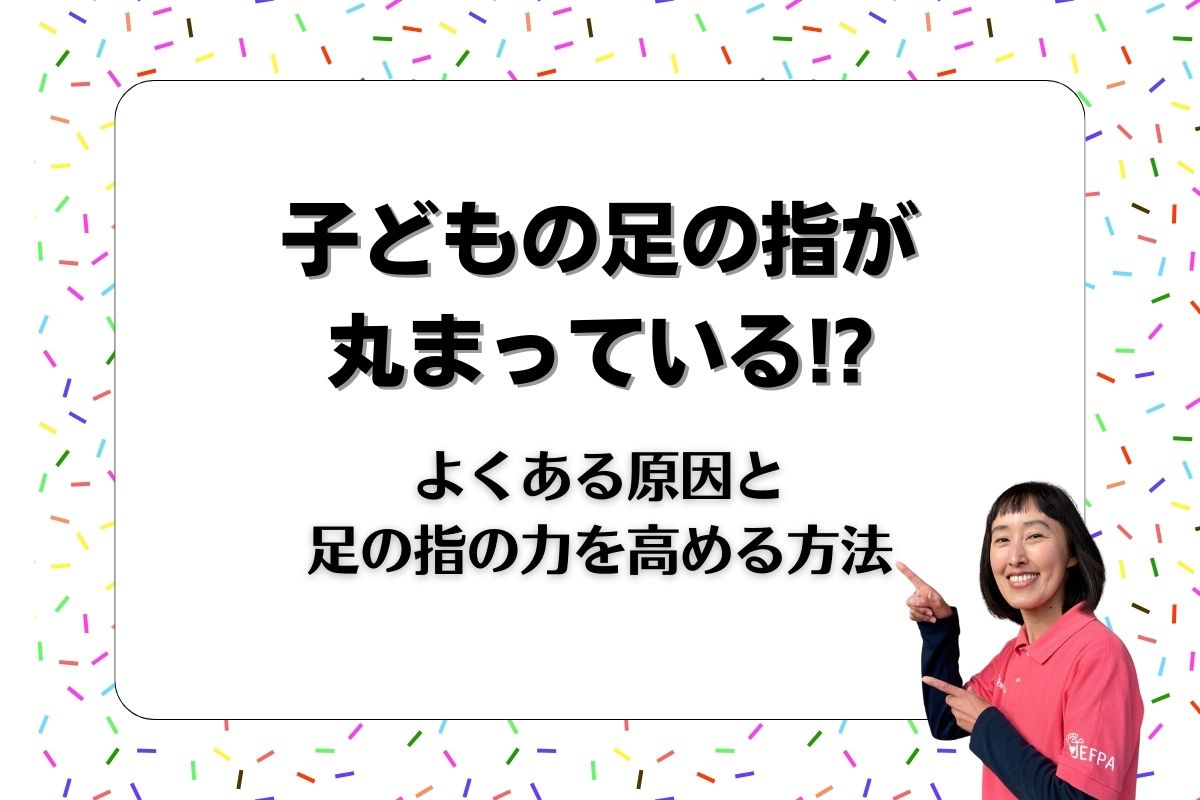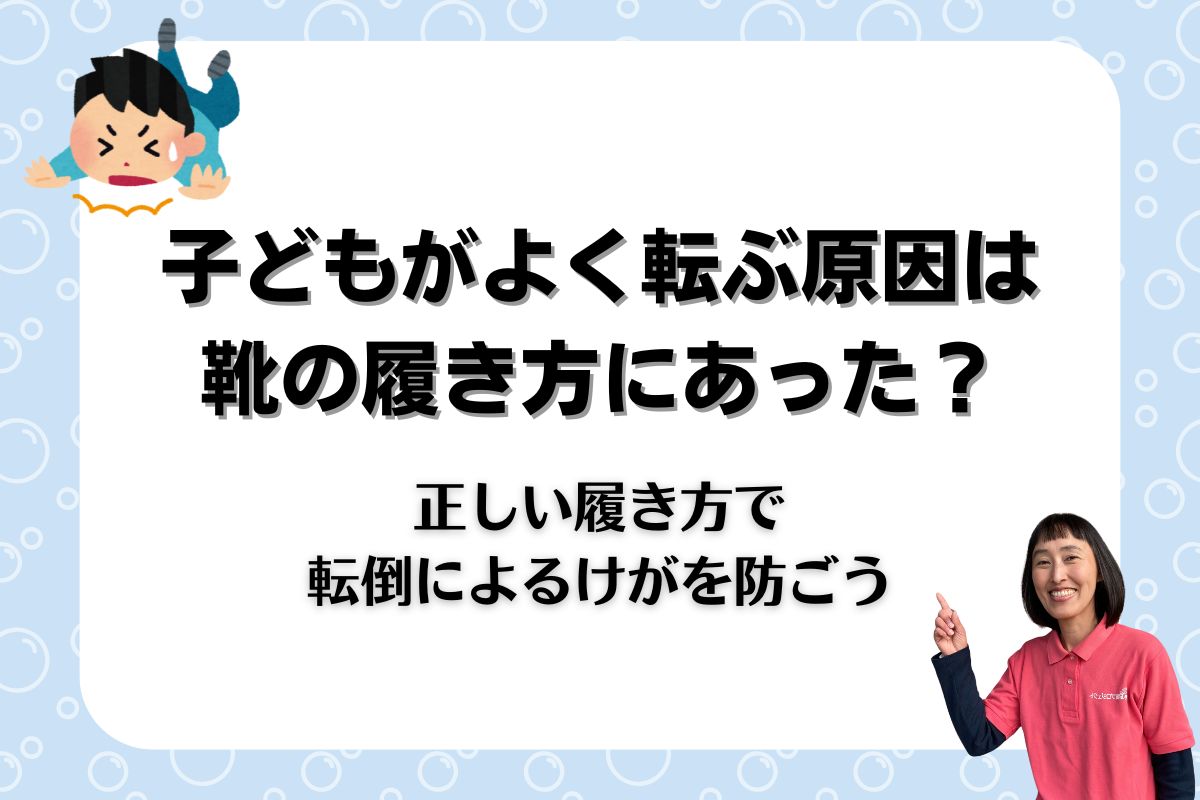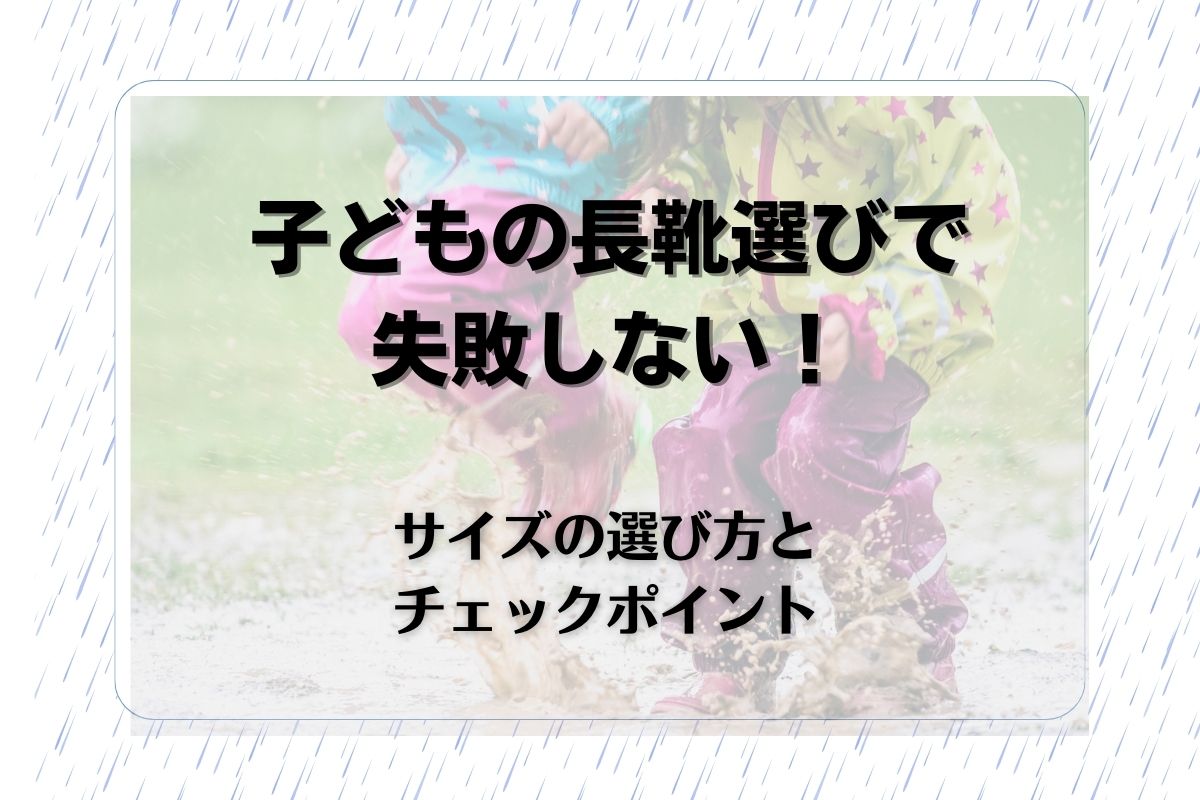
こんにちは! 足育アドバイザーの成田です。
メールマガジンの読者様から「長靴のサイズの選び方と、手頃な値段で購入できるものがあったら教えてほしい」というご質問をいただきました。
雨の日に欠かせない長靴ですが、成長途中でまだ未熟な子どもの足にとっては、意外と大切な存在です。
この記事では、その声にお答えしながら、長靴選びのポイントをお伝えします。
長靴サイズの選び方の基本
長靴のサイズの選び方と、手頃な値段で購入できるものがあったら 教えて頂きたいです!
本当に一時的に履く靴なので、どこまでこだわればいいのかよくわからないんです。
西松屋や、バースデイなどで売れているもので十分なのか…それとも、スタンプルなど メーカーのものがいいのかなと。
いろいろ見るんですが、形もそれぞれ違いますし、インソールがあったり、なかったりだとか、どういうところに注意して購入したらよいのでしょうか。
長靴のサイズチェックの4つのポイント
裸足で測った足のサイズに5mmから1cmを足したサイズを試してみましょう。
同じサイズが書いてある長靴でも、実際のサイズ感は異なるので、必ず履く人の足と合わせてサイズを確めてください。
中敷でサイズを確認できるか
中敷(いわゆるインソール)がついている長靴は、中敷を取り出してサイズの確認ができるのでおすすめです。
長靴のサイズ選びも、普通の靴と基本は同じで、つま先に適度な余裕があり、足の幅にちょうど合うものを選びます。
中敷を取り出し、両足を乗せて立ってみて、チェックしましょう。
中敷を使ったサイズ確認のやり方は、次の記事をご覧ください。
つま先に適度な余裕があるか
つま先の適度な余裕は、靴の大きさに比例して変わります。
靴のサイズが15センチ以上の場合はつま先の余裕が1cm程度、靴のサイズが15センチ未満の場合はつま先の余裕が8mm程度あることを目安に選んでください。
つま先に余裕がありすぎると、長靴の中で足が前にずれてしまって歩きにくいので、ワンサイズ小さいものを試してみるか、別の長靴にしましょう。
幅が足に合っているか
中敷に足を乗せた時に、足よりも中敷の幅が狭いものは、幅がきつすぎます。
逆に、中敷よりも足の幅が狭いものは、幅が広すぎて靴の中で足が左右にぶれてしまいます。
幅があまりにも合わない場合は、他の長靴を試しましょう。
最後は試しに履いてみること
中敷を使ったサイズ確認が大丈夫そうなら、履いて歩いてみて、歩きやすさを確認しましょう。
中敷でのサイズは良さそうでも、足がぐらぐらしたり、長靴が脱げそうになったりすることもあります。
そういうときは、他の長靴を試した方が良いです。
長靴の形がストンとまっすぐなものよりも、足首のあたりが絞られたものの方が、フィット感は高いです。
長靴を選ぶ時にチェックしたい3つのポイント
最も重視するのは「すべりにくさ」
長靴は雨の時に履くものです。
タイルの上など、雨で濡れるとすべりやすい場所もありますので、普通の靴選び以上に靴底の耐滑性(すべりにくさ)は重視しましょう。
次に重視するのは「歩きやすさ」
長靴の素材は主に2種類あり、ゴム素材は柔らかく伸びが良く、塩化ビニル素材は軽くて汚れにくい特徴があります。
素材のもつ特徴や長靴のデザイン、そしてお子さんの足との相性が組み合わさって、歩きやすさは変わります。
いろいろな長靴を試してみて選んでください。
長靴の丈も事前にチェックしましょう
保育園や幼稚園、学校に通っている場合は、下駄箱に長靴をしまうときにどのくらいの丈まで入れられるかをチェックしておきましょう。
1人分のスペースの高さが低くて、丈の長い長靴だと中に入らない場合があります。(私も一度失敗しました…)
長靴はベルトやひもで足を固定できないため、どうしてもフィット感が弱めです。
そのため、普段履きには適さず、必要な時(雨の日)に限定して使うのがおすすめです。
まとめ
今回は「手頃な値段で購入できるものがあったら教えて」という質問もいただきました。
確かに値段は気になるところですが、靴の値段は中敷の有無や素材、デザインなど、いくつもの要素が重なって決まります。
だから、値段で選ぶのではなく、
- 足に合うサイズかどうか
- 靴底が滑りにくくなっているか
- 歩きやすいかどうか
この3つを意識して探してほしいと思います。
長靴は、ベルトやひもで足に固定できない分、足に合うものを見つけるのは意外と難しいと感じます。
だからこそ、ネット購入ではなく靴屋さんの店頭で、複数の長靴を試し履きしながら「いちばん足に合う一足」を選んでいただけたらと思います。