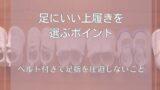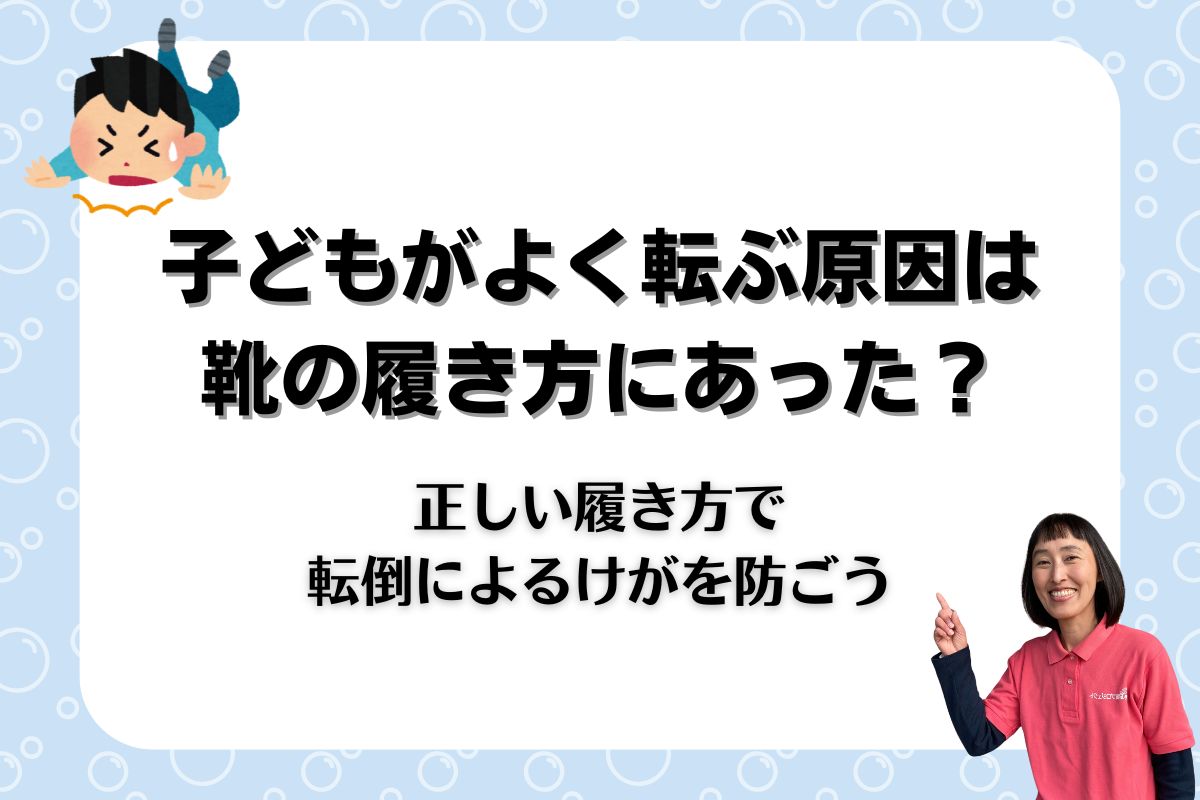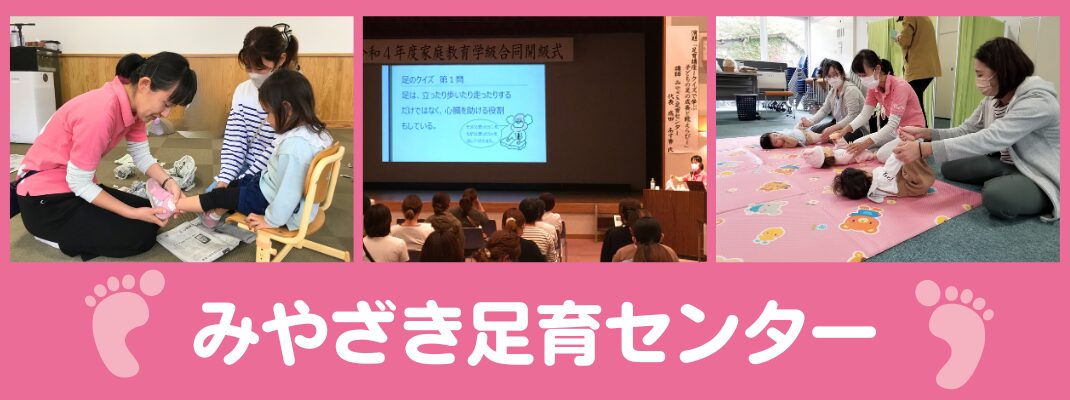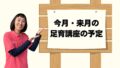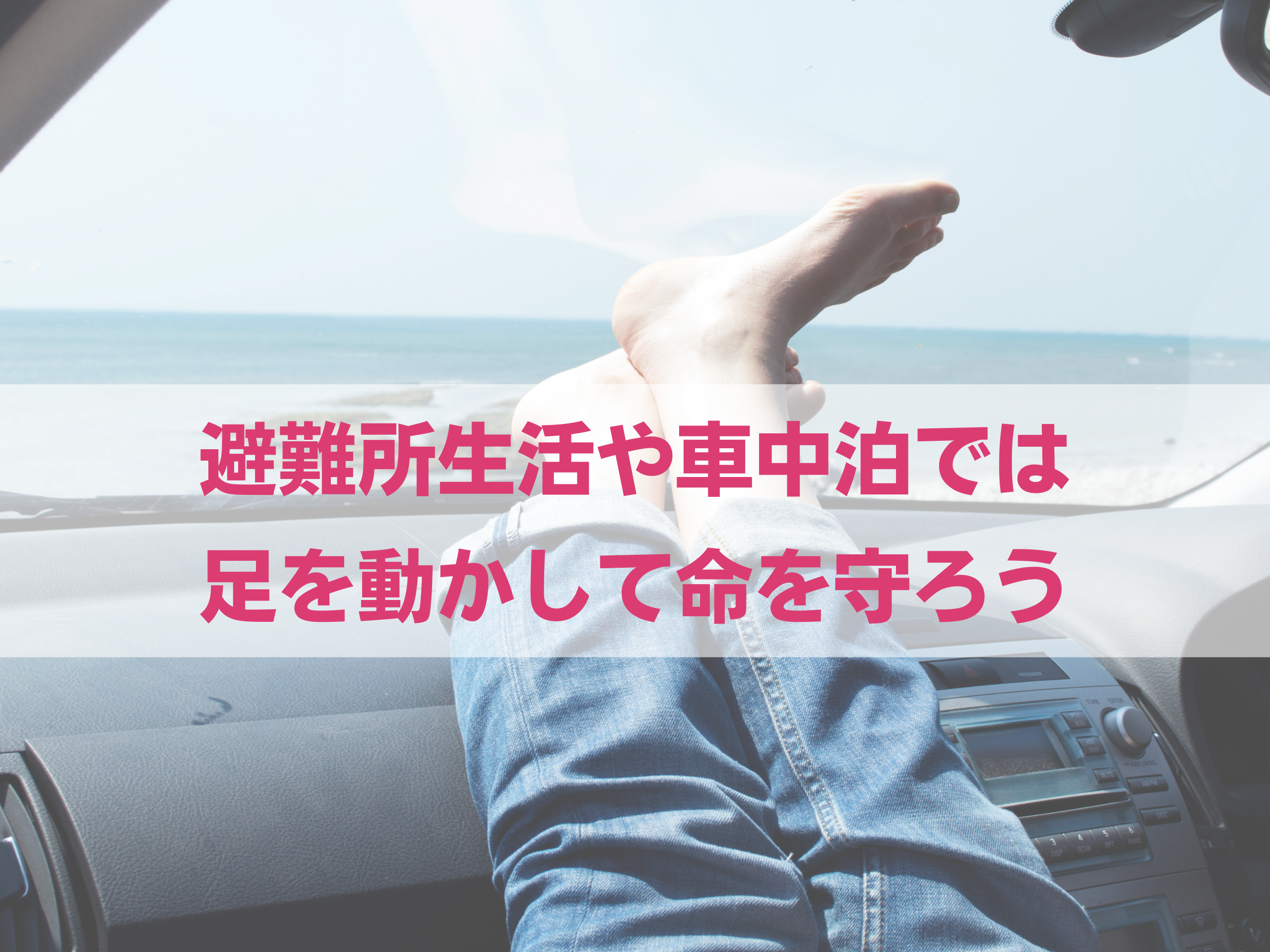
こんにちは、足育アドバイザーⓇの成田あす香です。
毎年9月1日は「防災の日」です。
災害はいつどこで起こるか分かりません。
いざという時のための備えをされている人は多いと思いますが、「命が助かった後」のことまで考えたことはありますか?
私が理事を務めるNPO法人日本足育プロジェクト協会では、熊本地震を経験した足の専門家を講師に迎えて、2023年8月に「命を守る減災的フットケア」という勉強会を開催しました。
避難所生活や車中泊避難では、助かった命を守るために「足を動かす」ことが大切です。
講師の竹永志保さん(爪と足と歩行の専門店 フットサロンシンシア代表)から伺った、震災関連死を防ぐためのポイントをご紹介します。


命を落とすこともある「エコノミークラス症候群」
エコノミークラス症候群は、狭い場所で長時間同じ姿勢を続け、脚を動かさないことが原因で生じる病気で、正式には「肺血栓塞栓症」という病名です。
脚を動かさずにいると、脚の静脈に血栓(血の塊)ができやすくなり、その血栓が肺血管に流れて血管を詰まらせ、最悪の場合は命を落とすこともあります。
若者から高齢者まで、誰にでも起こり得るものですが、とくに高齢者はより注意が必要です。
過去の震災でも、避難生活の中でこの病気を発症し、突然体調を悪化させる人が多くいました。
避難所や車中泊ではのリスクが高まりやすいため、意識して予防することが大切です。
予防のポイント(1)体を動かす
ふくらはぎは「第2の心臓」とも言われ、歩くなどの動きを通してこの筋肉が収縮されることで血流を促します。
避難生活の中では、食事の受け取りやトイレへ行くついでに歩く、ラジオ体操をするなど、体を動かす意識をもつことが必要です。
その場から動けないときでも、足踏み、つま先立ち、足の指のグーパー、足首を曲げ伸ばしするなど、こまめに足を動かすことが大切です。
起きている間、30分以上座りっぱなしの時間が続く場合は、 30分おきに立ち上がって体を動かすようにしましょう。
予防のポイント(2)水分をとる
水分が不足すると、血流が滞りやすくなります。
熊本の震災では、遠くて暗くて臭い仮設トイレに行きたくない…と水分を控える人が多かったそうです。
しかし、命を守るためには、意識して水分をとるようにしましょう。
なお、災害時は性犯罪も多く起こるため、特に女性や子どもは複数人でトイレに行くように心がけてください。
糖尿病や透析治療を受けている患者さんが周りにいたら
もしも、糖尿病や透析治療を受けている患者さんがいたら、足をよく見て、触って、異常がないかを確認してください。
このような人たちは、小さな異変があっという間に悪化し、細胞組織が死んでしまう壊疽(えそ)という状態になりやすいリスクを抱えています。
壊疽が広範囲になると、治療もできず、命を守るためには足を切断するしかなくなってしまいます。
傷や水ぶくれ、冷えやむくみ、かゆみ、皮膚や爪の変色などに気付いたら、些細なことでもすぐに医療関係者につないでください。
まとめ「逃げられる足でいるために」
竹永志保さん(爪と足と歩行の専門店 フットサロンシンシア代表)を講師に迎えての足育アドバイザーⓇ勉強会「命を守る減災的フットケア」からお届けしました。
竹永さんの話で印象的だったのが「次の大きな揺れが来た時に逃げられる足でいてほしい」という言葉です。
大きな地震の後は「1カ月程度は大きな地震に注意を」とも言われています。
助かった命を守るために、ぜひ足を意識して動かし、足の状態に気を配ってください。
普段から体を動かす習慣、足に気を配る習慣をもつことが、「災害時に逃げられる足」を育み、災害後の足の健康を守ることにもつながります。
この防災の日をきっかけに、足もとの習慣も見直してみませんか。
足を動かすことは、特別な準備やグッズもいらず、今日からすぐに始められる防災対策です。